こういった疑問に答えます。
現代における中学生の不登校事情

中学生の不登校の総数が増えているのか、減っているのかご存知でしょうか?
少子化が進んでいる今、全体数に関しては減っているのではないかと考える人もいることでしょう。
しかし、生徒の数は減っているのに、不登校生徒の総数は増えているのが現状です。
この記事では、登校をしぶっているいるような“登校しぶり”の子どもや実際に不登校の状態になっている中学生を持つ親が、少しでもその状況を改善できるような方法をご紹介します。
ぜひ、焦らず、一歩一歩進んで行きましょう!
なぜ中学生で不登校が増える?
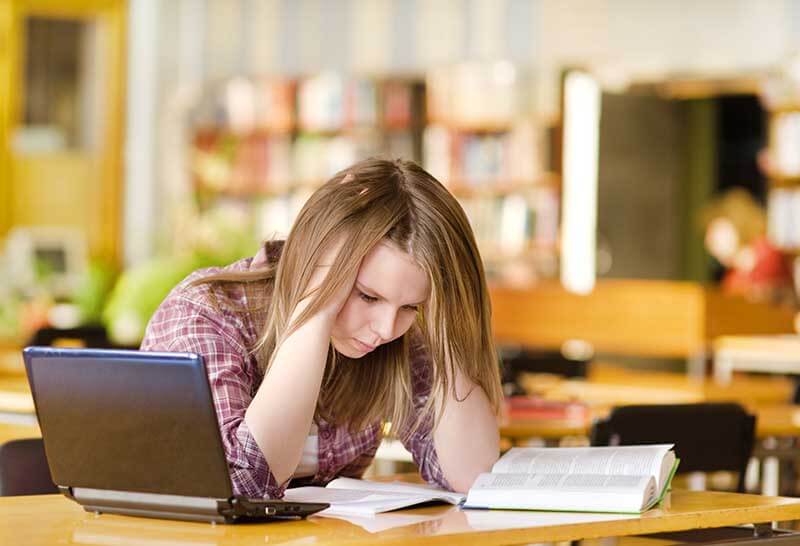
不登校についてお話をする前に、まずは不登校の定義について明らかにする必要があります。文部科学省によると、不登校の生徒について、
「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」
と定義しています。
そして、この不登校の生徒数が中学1年生になると一気に増加してしまいます。
これは“中一ギャップ”と呼ばれていますが、なぜこのような現象が起こってしまうのでしょうか?
中学生になると、より勉強が難しくなったり部活動が本格化しますよね。
また、先生との関わり方が変わったり、友達付き合いも変化したりすることがあります。
つまり、これまで以上に子ども自身の社会的な能力が求められるとも言えます。
そのために中学校に上がると、不登校になってしまう生徒が多いのかもしれません。
中学生が不登校から復帰するためには

それでは、どうすれば中学生が不登校から復帰することができるのでしょうか?
ここでは大切なポイントを2点ほど、ご紹介します。
子どもの心のエネルギーを満たす
子どもが不登校になる原因の一つとして、心身のエネルギーが枯渇してしまっている点が挙げられます。
特に心のエネルギーが不足していると、集団生活や勉強についていけなくなる場合が多いです。
そのため、まずは子どもに愛情を注いであげて下さい。
食事を作ってあげたり、一緒に会話をしながら食事をするのも良いでしょう。
また、やりすぎない程度のスキンシップも愛情表現の一つとしてオススメ。
休日の日などに子どもと一緒にお出かけをするのも、あまり外出をしない不登校の子どもの気分転換に良いでしょう。
いくつか例を出しましたが、共通しているのは“ともに”何かをすることです。
愛情がこもっていれば、会話をするだけでも子どものエネルギーは充電されて行くはずです。
学校に行かせること、勉強をさせることは、子どもの心のエネルギーが十分に充電されてからにしましょう。
少なくとも、段階的に学校へ行ければ、それはすごいことだと言えます。
子どもが愛情に溢れて、心身ともに元気になれば、きっと自然に前へ進んで行けるはずです。
親自身が充実した生活を送る
子どもが不登校になると、親自身も落ち込んでしまったり、自分を責めてしまうことがあります。
しかし、一番不安で困っている人は誰でしょうか?
それは、不登校になっている子ども本人のはずです。
子どもが不安な時に、親も自信のない暗い顔をしていては、子どもはもっと不安になってしまいます。
親である、あなた自身の生活を豊かにして下さい。好きなことをして下さい。自分を喜ばしてあげて下さい。
そうすれば、きっと家族や子どもに対して、もっと明るく愛情深く接することができるでしょう。
子どもは親を見ながら、成長します。
親が充実していれば、きっと子どもだって充実した生活を真似して行くことでしょう。
以上で子どもを不登校から復帰させるポイントを説明しました。
ただし、一つ注意点があります。
それは、いじめが原因で学校へ行けない場合。
いじめが本当にエスカレートすると命の危険すら出てきてしまいます。
そのような時は、まずは当面学校を休むという対策も、いじめから避難する一つの手段として正しいはずです。
一度、自宅へ避難してから学校の先生などに状況を説明して、対策を練りましょう。
不登校からの復帰を焦らないことも、また重要だと言えます。
不登校中の中学の勉強はどうする?
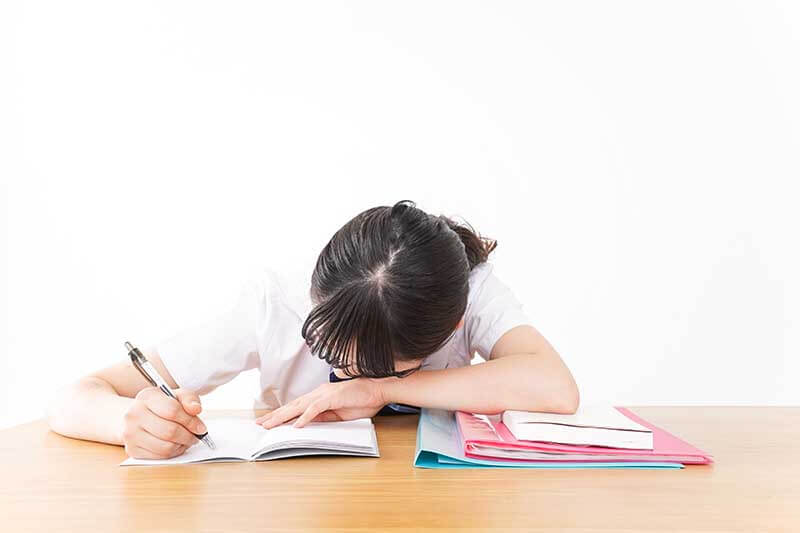
不登校中の勉強の遅れについて、とても心配する方が多いかもしれませんね。
ただし、まず一番大切なことは、子どもの心と身体のエネルギーを補充してあげることです。
心身が充実していなければ勉強どころではありません。
そして、子どものエネルギーが十分に満たされた後、ひきこもりや不登校の生徒を専門的に扱っている家庭教師や塾などに教育・学習を依頼することもオススメです。
その他にも、不登校の生徒が通っているフリースクールなどが存在します。
また近年では、ICT(コンピューターヤインターネット、遠隔教育システム)、郵送、FAXなどを活用した学習活動も、出席扱いにできる場合があります。
オンライン学習などに興味がある人は、一度検討してみると良いかもしれません。
ただしお金がかかる場合も多いので、子どもの気持ちがしっかり充実してから、子ども本人とじっくりと話し合って決めると良いでしょう。
無料体験ができるオンライン家庭教師についてはこちらで紹介しています。無料なのでとりあえず試してみるのがいいかと思います。

不登校でも中学は卒業できる?

中学生であるならば、留年や退学は基本的にはありません。
また、出席日数も卒業には関係がないため、不登校でも中学校の卒業は可能と言えます。
※私立中学校については、対応がそれぞれ違う場合があります。学校の先生や進学担当者にご相談下さい。
ただ、卒業は可能ですが、中学校との適切な連携は大切だと言えます。
もちろん、学校は子どもにとって必ずしも行かなくてはならない場所ではありません。
小学校と中学校に通う9年間は義務教育と呼ばれていますが、子ども自身は適切な教育を受ける権利を持っているだけです。
この“義務”という言葉は、大人側が子どもに適切な教育を受けさせなければならないという意味で使われています。
適切な教育を受けるために、フリースクールなどの不登校生徒を対象とした学校に通ったり、オンライン学習を受けることも選択肢の一つ。
ただ、中学校側と連携した上でそれらの選択肢を模索したり、利用することで生徒にとってもメリットになる場合があります。
例えば、フリースクールやオンライン学習での勉強を中学校での出席日数にカウントしてもらえることがあるからです。
子どもの将来の役に立つように、中学校を上手く活用して行くことが大切です。
まとめ
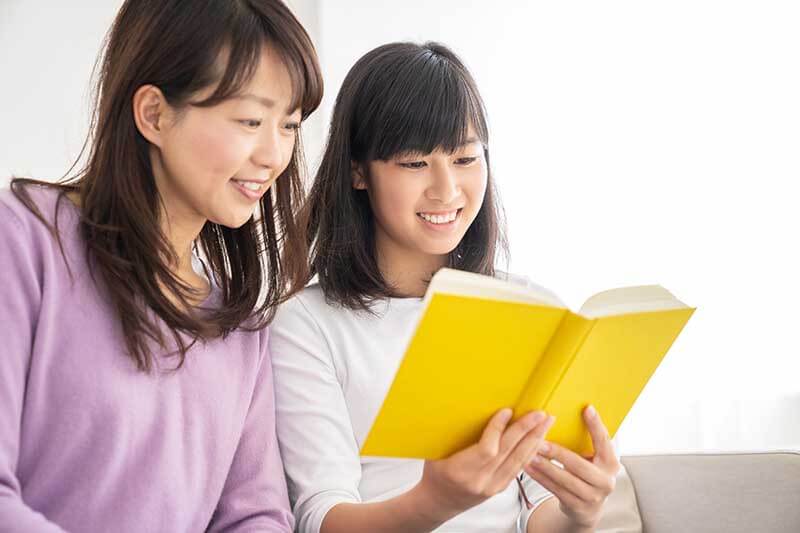
先ほど不登校でも、中学校自体は基本的に卒業できることをご説明しました。
ただし、一番大切なのは、子どもが卒業後にどうするかということです。
中学校卒業後は、進路の選択肢の幅が一気に広がります。
ただ、ほとんどの不登校経験者は高等学校に進学しています。
2014年に発表されたデータでは、不登校経験者の約85%が高校に進学しました。
参考:文部科学省ホームページ 「不登校に関する実態調査」 ~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~(概要版)2014年7月9日
高等学校の中だけでも、全日制・定時制・通信制などの選択肢があります。
また、高等学校へ進学しないで高卒認定試験を目指すことも可能です。もちろん、すぐに働きたければ、就職活動をすることだってできます。
ぜひ、子どもとじっくり話し合ってから、今後の進路を決めて下さいね。
(参考文献)
・2020年 主婦の友社 菅野純 あらいぴろよ「子どもが学校に行きたくないと行ったら読む本」
・2019年 講談社 下島かほる 「登校しぶり・不登校の子に親ができること」









